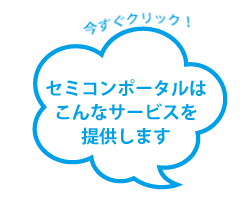AIや仮想空間技術を用いた環境・安全教育(後編)
前編(参考資料1)でプラント設計、特に工場建屋設計時の注意事項の一例をまとめて記述した。具体的には、「想定外」だった化学薬品自動配送タンクの配管が外れた事故事例を題材にして、生成AIや仮想空間技術を駆使して、その事故を「想定内」にし、対策を床構造設計時に織り込む環境・安全教育用教材を提案した。
オンサイトプラントに対するリスクマネジメント
後編では前編同様に一般の半導体製造技術者には、普通は「想定外」になるだろうと思われるオンサイトプラントの事故を事例として、環境・安全技術教育の題材を提供する。オンサイトプラントとは顧客工場敷地内にベンダー企業が原材料製造装置を設置し、そこから顧客工場に原材料を直接供給するプラントを指す(参考資料2)。本稿は具体例として、ガス会社が液体窒素製造装置を半導体工場敷地内に設置して、そこから半導体工場に液体窒素や、液体窒素から気化させた窒素ガスを供給するオンサイトプラントを例として、そこの事故によって引き起こされた半導体工場の災害に関する環境・安全技術者教育用の題材である。
オンサイトプラント側が起こす事故であり、半導体工場側に直接の責任はない。しかしそれでも原材料が止まれば半導体工場が動かなくなり、半導体製造企業の顧客には製品が届かなくなる。その事故次第によっては、半導体製造企業が倒産してしまう。従ってこのような事故に対する事前の対策を立てておくことも、半導体製造技術者として避けて通れない。
具体的に話を進めよう。ある堅実で中規模な企業(以下いろいろな会社が登場するので、A社と記す)を想定してもらいたい。A社は材料技術を基盤とした会社であり、本格的な半導体製造は未経験である。そこでは創立70周年を記念して、他業種への事業拡大を模索することになり、その一つの新規事業候補として半導体事業が試みられた。本稿でもあくまでも架空の話として、考えてほしい。
実験室規模のラインは既にA社内に作られていたが、最先端の微細加工ラインには程遠く、投資してそうしようとしても、その時点の社内留保金では少なすぎる。そのため許される範囲内の資金で中古設備を買い集め、それなりの微細加工度で作れるデバイスの製造ラインを構築し、そこで得た利益を基に、徐々に微細加工技術を磨き、ゆくゆくは利益率の高い先端デバイスを生産できる工場にしようという目標を掲げ、堅実な長期ビジネスプランを作成した。そのうえで全社横断的なコンセンサスを得て始めた事業である。
A社では半導体に関しては技術力も不十分で、作業者も量産教育をなされていない。しかし熱意のある人材は多いので、そのような技術者と作業者を集めてプロジェクトが結成された。組織としてはA社内にこのプロジェクトが事業部門に並ぶ形で設置され、そのプロジェクトが既設実験ラインをさらに整備拡張して、デバイス製造ライン(以下A社半導体工場と記す)として傘下に持つという形をとることになった。
本稿では個別の説明を省略するが、ご多聞に漏れずこのA社半導体工場が稼働に至るまでも、数多くの試練を乗り越えねばならなかった。ともあれ親会社、関係会社から多くの援助を受けながら艱難辛苦の努力の結果、この A社半導体工場は大企業T社のゲート・ドライバ(参考資料3)を受注して、T社の認定も頂き、量産する段階までにやっと漕ぎつけた。
そのA社半導体工場では、当初はタンクローリで運ばれてくる液体窒素を用い、そこから蒸発する窒素を精製して高純度窒素ガスにして使っていた。一般に半導体工場では工場内の多くの製造設備で高純度窒素ガスを使用している。しかも液体窒素を蒸発させた窒素ガスといえども、いったん窒素精製装置を通して更に高純度化しなければ、半導体レベルの高純度ガスとしては使えない。
A社半導体工場のゲート・ドライバ製造が軌道に乗った頃、ガス販売会社T商会から、長期的に見た経費節減のため、タンクローリでガス会社から液体窒素を運ぶより、ガス会社の液体窒素製造オンサイトプラントをA社内に設置して、そこで得た窒素ガスを直接A社半導体工場の窒素精製装置に導入し高純度窒素ガスにして、タンクローリによる運搬費を節減してはどうかという提案を受けた。A社内で検討の結果、現時点では半導体事業は赤字だが、まだ健全な赤字とも言える段階なので、早期に事業黒字化を達成するには、ここで原価低減策としてその案を採用しようという企画案が役員会を通過した。そこで大手ガス会社N社とO社の競争入札の結果、N社オンサイトプラントがA社の敷地に建設され稼働を始めた。
ある時、A社半導体工場の夏休みを使ってオンサイトプラントのメンテナンスをやりたいとN社から要請を受けた。A社半導体工場としても生産計画に支障はないので、了承し進めて頂くことにした。ところがN社から作業員が来てメンテナンスを行った時に、それこそA社半導体工場から見て全く「想定外」の事故が発生した。何を間違えたのか、メンテナンス作業終了時にその作業者は、N社オンサイトプラントからA社半導体工場に窒素ガスを送り出す配管に、本来接続するべき窒素ガス配管ではなく、空気を送る配管を接続して、ミスに気づかずに帰ってしまったという、A社半導体工場はもちろん、専門のガス会社であるN社でも到底考えられないミスであった。
A社半導体工場の窒素精製装置ではニッケルを触媒として窒素精製を行っていた(参考資料4)。通常なら微量の酸素を窒素精製装置で除去するのだが、そこに大量の酸素を含む空気が流れ込んだため、窒素精製装置の能力限界を越し、配管内が高温となり火災が発生した。そのためテフロンフィルタが燃え、結果としてA社半導体工場内で高純度窒素ガスを使用しているあらゆる半導体製造設備の入口のフィルタまで、テフロンの燃焼煤が飛んでくるという大惨事に発展してしまった。
A社半導体工場では夏休みといえども、休み明けにすぐ工場が稼働再開できるように、電力を落としながら無人の維持運転をしていたため、万一の事故に備えて、管理職技術者が当番で巡回するシステムになっていた。その日の第一発見者はその当番で巡回していた工場設備に詳しい技術課長で、窒素精製装置の配管が赤くなっているのを発見したため、直ちに上司に連絡するとともに、A社半導体工場窒素精製装置の入口バルブを閉じてくれたので、配管外への類焼は免れたが、当然A社半導体工場は稼働停止せざるを得なくなった。
経理上に及ぼす影響
いかに整然とした製造ラインを構築しても、いかに作業者訓練を行っても、生産するモノを流せなければ日々損が発生し累積される。そのうえ全窒素ガス配管を新しい配管に交換して工場を再開しても、大企業T社に納入するためには、半年以上かかる厳正なライン認定試験を再度受けなおさねばならない。その間も工場を停めるとなると、それ以前からの累損の上に、更に莫大な損が積み上がることになる。しかも実験ラインから量産ラインにするため中古設備ではあるが、ゲート・ドライバを生産できるほどの諸設備を整えたので、固定資産額も膨らんでいた。
前記のようにそこまで来るには幾多の事故も経験していた。しかしそれらは自力で解決できて一つ一つ乗り越えてきたが、それによる累損は積み重ねられていたので、このオンサイトプラント事故がA社の半導体事業にとどめを刺すことになった。つまりいくらその事故はガス会社N社のオンサイトラインに起因すると言っても、また直接A社半導体工場の責任ではなくても、A社本体が経理的に上記累損に耐えられなければ、A社としては半導体事業を撤退させるしか方法がなく、とうとう半導体事業へのプロジェクトは閉鎖に追い込まれてしまった。T商会の努力もありガス会社から賠償金も支払われたが、それはA社のその後予想される累損に比較すると、全く焼け石に水の額であった。A社内の他事業から見れば、半導体プロジェクト責任者の危機管理不足、リスクマネジメントの怠慢ということになるので、その誹りは甘受せざるを得ない。A社取締役会でのごうごうたる非難を浴びながらの撤退である。
熱心な半導体技術者の中には他社から来てくれた技術者もいた。また作業者たちにも近隣の関連半導体工場で実習するという苦労をお掛けしていた。また何よりもA社半導体工場の作業者訓練に協力していただいた恩にも報いることができなくなった。ラインの立ち上げに苦労した大勢の方々の努力もこれで水の泡である。事故第一発見者の技術課長の防災功績は大なるも、事業撤退のためその功は評価されるには至らなかった。その前に経理上の都合で、半導体事業はA社から分社化されていたので、半導体事業のトップは代表清算人の職責を担うことになった。
AI、VR技術を活用する契約書の作成
さてこのような事故をいかに防ぐかということを考えて、それを環境・安全教育用の教材にする案を考えてみたい。作業ミスはメンテナンス時のような、非日常作業時に起こりやすい。非日常作業であっても自社内であれば、過去の経験を生かして種々の事故防止策がある。しかし上記N社オンサイトプラントは、その敷地周囲に柵が設けられていて、普段は施錠されており、A社から見るとある意味で治外法権のような区域になっている。そこのミスが起因する事故に対しては、A社半導体工場の製造技術者はどうすればよいだろうか。どうすれば危機管理不足、リスクマネジメントの怠慢を防げるだろうか。
まずメンテナンス時に配管接続ミスを起こさないよう、それぞれの配管に番号札や色別した識別票なりラベルを付ける処置を講じるのは、ガス会社Nの責任であるが、本稿ではA社のやるべきことを主体に考えるため、まずガス会社との契約時に遡って、そこでの注意点を3点記述する。
Action1) オンサイトプラント企業にメンテナンス作業者教育を徹底させることを契約書に明記する必要がある。単に作業者教育をお願いするだけではなく、その作業者教育の進め方にも踏み込む必要がある。どういう手段で作業者教育を行うのか、どういう頻度で教育を行い、いかなる手段でその受講者の技術到達度を測定するのか。また教育をした証拠と、教育を受けた証拠はどう残すのか、その更新はどうするのかまでしっかり把握して、オンサイトプラント会社に危機管理意識を共有してもらわねばならない。
現在ならメンテナンス作業訓練もAI、特に生成AI やバーチャル技術を使って行える(参考資料5)。後編でも前編にならってバーチャル技術をVRと記すが、ここでは単なる狭義の仮想現実VRだけではなく拡張現実(Augmented Reality:AR)や複合現実(Mixed Reality:MR)など、あるいはそれらを適宜含んだExtended Reality(XR;あるいはCross Reality CR)をも含む、広義の仮想現実の意ととらえてほしい(参考資料6)。このようなVR技術を駆使してでも作業者訓練を徹底させることを契約することも、事業維持のための危機管理としては必要事項である。
A2) 作業者教育の効果を確実にするため、実際のメンテナンス時には、上記のような最先端技術を駆使した訓練済みの作業者を少なくても1名以上含ませて、メンテナンスに派遣することを、契約書に織り込む必要がある。特定の作業者に教育だけして、実際にはその作業者が含まれないチームがメンテナンスに来るのであれば、意味がない。
A3) 複数の作業者で作業することを契約書に織り込むことも必要になる。しかし現実問題として大企業の半導体企業相手なら、オンサイトプラント企業もそれなりの人数を派遣するだろうが、小さな半導体ラインを相手にする場合、多人数を派遣せよと要求してもオンサイトプラント企業にとっては経理的に負担になり、ひいてはメンテナンス費用として上乗せされるだけである。
しかしこれもまた現在のAI、VR技術を使えば、たとえ実際にオンサイトプラントのメンテナンス作業に来る作業者が少人数でも、極端に言えば1人であっても、現地で作業する者とガス会社のコントロール本部とを結んでその作業を監視、監督することにすれば、実効的に2人作業、あるいは2人以上の作業にすることもできるはずである。
既にAIやVR技術を用いて、海外工場を立ち上げた報告もある(参考資料7)。このような管理システムの実行をオンサイトプラント企業、本稿の場合はガス会社にしっかり要求して、作業手順を監視してもらうことも必要である。それがオンサイトプラント側でできなければ、自社の倒産を避けるためには、メンテナンス費用が上昇しようとも、2人(あるいはそれ以上)派遣して作業をするように依頼せざるを得ないだろう。オンサイトプラント企業にとっても事故を起こした場合の賠償金支払いを考えれば、AIやVR投資は、他の多くの同様な顧客にも使えるので、微々たる投資であろう。
自社での危機管理・リスクマネジメントの徹底
翻ってこのような事故は、上記のように事業の存亡に関わるので半導体製造企業側でも徹底した危機管理が必要である。
以下は半導体製造企業内での是正処置3点である。
Corrective Action1) まず自社内でも、そのオンサイトプラントが事故を起こした場合の対策を策定しておき、日頃の訓練に織り込んでおく必要がある。定期的な防災訓練などにもその項目を入れて置き、折に触れオンサイトプラントの作業員、あるいは技術者にも参加してもらって、事故時の具体的な対処手順などの確認とトレーニングをしておくとよい。上記の例では技術課長の適切な処置で、建物の火災に至る惨事を免れたが、いつまでも管理職個人の厚意や力量に頼っているのは危険である。これは前編の場合も同じである。
場合によっては地域の消防署などとの連携も必要になる。地域の消防署に訓練報告書を出しておくだけでも、社員の防災意識の継続と緊張感維持には効果がある。
CA2) その上でそれをしっかりシステム化して運用するために、例えばISO14001(参考資料8)などの規定を活用すべきと考える。ISOは高額な審査費用と審査準備時間を必要とするので、過去ISO9000sの時代に、ISOは単に審査機関側の経営持続のためではないかと誤解され、不評を買った時期がある。しかしISOはそうではなく、自分たちが決めたシステムが完全に実施されるようPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルがきちんと回わされているかという審査をするためのものなので、経営上の利益と直接には関係しない。しかしいったん事故が発生した場合のことを考えると、特にISO14001の考え方が非常時対策としては大変参考になる。例えばISO14001 の要求事項を勉強するだけでも良い。また内部監査制度を作って置けば、経費も掛からず、同じ効果をあげられる。
CA3) 半導体製造企業側の管理者教育も重要になる。上記のようにA社半導体工場には直接責任がない原因による事故でも、それが顧客に影響を及ぼすときは、危機管理不足の責任と、リスクマネジメント管理責任を問われる。その意味で半導体製造技術者といえども管理者教育は避けては通れない。そのためにはこれからのリーダーは、前記A1)やA3)にて記した契約書作成時にかかわるAIやVRについては、概略の理解をしておかねばならない。そのためのテキストや教育カリキュラムの整備も必須となる。
上述した本稿題材も、特にA1)〜A3)やCA1)〜CA3)は、半導体製造ライン関係者育成用の教材作成には参考になる素材と思う。後編ではオンサイトプラントの事故事例に絞って記述したが、半導体製造には特殊ガスや多種化学薬品を使う。それが外部に漏れた場合の環境・安全教育も極めて重要な課題であることに触れておきたい。環境・安全は製造設備や製造工場内だけの問題ではなく、工場外部にも影響を及ぼす場合もある。例えば農業地帯に立地された工場では農業用水路に薬品や油が漏れると地域の社会問題になる大きな事故になる。その意味で環境・安全教育の重要性は半導体要素技術の重要性に勝るとも劣らない。それを念頭に置いて、勘と経験に頼らず、最先端のAIやVR技術を駆使して科学的に事故を抑制する半導体製造者向けの教育、教材の整備作業が進むことを願っている。
そしてそれは大学院クラスの受講生にも使える「科学的な匂いのする」テキストやビデオ教材にも発展できる。前編でも記し、繰り返しになるが、筆者は恥ずかしいことにAIや仮想空間技術の実務経験がない時代に現役を終えてしまった。しかしネットやオンライン講習を受けると、その効果は理解できる。これからの時代は、この最先端の技術を駆使しない手はない。ぜひ本稿の前編、後編を合わせて、否、片方の編だけでも参考にして頂き、ここに記述した題材をバックグラウンドとして、AIやVR技術などの最先端技術を織り込み、具体的、かつ実践的な内容の教材、教科書を作成していただきたい。聴講生が目を輝かせるような環境・安全教育トレーニングを企画して、半導体製造技術者教育カリキュラムを実施していただきたいと願う。その暁には本稿で記述した事故が撲滅されるであろうことを心から期待したい。微力ながらも本稿がそのような半導体製造関連者の環境・安全教育に少しでも貢献できれば幸甚である。
謝辞:本稿作成のあたり、いつもの通り津田編集長のお世話になった。合わせ厚く御礼申し上げる。また本稿後編も筆者の実体験であるが、生成AIの使用規範が未定のため、架空の話として構成し、登場した管理職技術課長の実名記載を避けざるを得なかった。切り取った断片記事のみが独り歩きして、登場者に万一ご迷惑をかけることがないようにしたためであるが、前編同様、ここでも管理職技術課長が筆者を支えてくれたことに対する感謝と敬意の念は変わらない。
参考資料
1. 鴨志田元孝、「AIや仮想空間技術を用いた環境・安全教育(前編)」、セミコンポータル、(2024/10/02)
2. 例えば「窒素ガス供給オンサイトプラント(JNA深冷窒素発生プラント)」
3. 本稿の某T社とは関係ないが、ゲート・ドライバの一般的な解説としては例えば、S. Sapre、「絶縁型ゲート・ドライバとは何か、なぜ必要なのか、どう使うのか?」、Analog Devices、ADI Analog Dialogue
4. 例えば、「超高純度窒素ガスの製造方法及び製造装置」、JP2010235398A、Google Patents
5. 例えば、「製造業向けVR・ARソリューション」、NECソリューションイノベータ
6. Extended Reality に関しては例えば、「Extended Reality (XR) - Building AR | VR | MR Projects」、Udemy
7. 例えば(株)沖データの例、三島一考、「技術者が行けない! タイでの新製品量産を遠隔立ち上げしたOKIデータの挑戦」、スマート工場最前線、MONOist、(2021/03/02)
8. 吉澤正、「対訳ISO14001 環境マネジメントシステム」、日本規格協会発行、(2005)